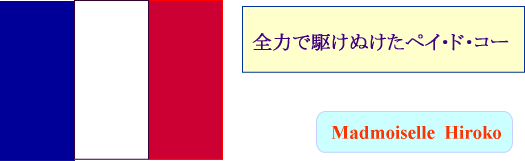
 <速報!2位入賞!> ⇔ 真ん中が優勝したアルジェリアの選手。 (ハリー・ポッターに似てるでしょ、だから ずっと日本選手団ではハリー・ポッター さん、とよんでいました) 私の反対が三 位のフランス人女性です。とっても嬉しく て、にこにこ笑っています。 DVDカバーガールはこちら |
| <レースレポートはこちら> FSGTスポーツ連盟の招きを受けて、5/15〜25の日程でフランスのロードレース「ツール・ド・ペイ・ド・コー」に派遣していただいた。4日間連続で6レース、合計約90キロを走る行程に同行メンバーは私を含めて4名。出発前日の東京での壮行会にて初顔合わせだったが、お互いの飲みっぷりで意気投合、なんの心配もない日本選手団となった。 15日夕刻パリ到着後迎えのバスで約2時間余り、北西部のノルマンディー地方へと向かう。バスには他国の選手団も乗りこんできて、足元を見ればすぐにランナーとわかる、みなランニングシューズをはいている。が、私はまだ少し緊張していて、会釈をするだけ。第一この人たちは何語を話すのかしら?  ⇔ ロードサイドにも大きな告知看板 ⇔ ロードサイドにも大きな告知看板サマータイムで夜の9時を過ぎてもまだまだ明るい。私が時差ぼけとサマータイムボケで完全に眠りこけているうち、選手村となる宿舎に到着した。あたりは見渡すかぎりの牧草地帯。築後100年は経っていそうな趣のある石造り・レンガ造りの建物が点在する。今回の宿舎は、バカンス・ビレッジと呼ばれるコテージ。個々に2〜3室のベットルームを持った独立のとんがり屋根の建物で、日本選手団にも1棟が与えられた。  ⇔ コテージの中庭にて ⇔ コテージの中庭にて食事は選手が一堂に会することの出来る食堂にて。入り口には「歓迎」のフランス語とともに万国旗が描かれた手作りのプレート。迎えてくれたのはサンタおじさんのようなにこやかなシェフ。滞在中何度も足を運ぶことになるであろうダイニングルームに、「ボン・ジュール」と元気印で飛びこんでいった。まだ20名足らずの選手たちだ。まずはビールとワインで乾杯。本当にフランスまでやってきたことに感無量。  ⇔ 陸上競技場にて ⇔ 陸上競技場にてレースまでの3日間はのんびりと過ぎていった。鳥のさえずりで目が覚め、コテージの外に出てみると朝もやの中に広がる牧場風景。小径にジョギングに出かけ、背丈よりも高い黄色の菜の花にうずもれてしまう。ノルマンディーの牛たちに挨拶するのもフランス語かな?天気も気候も申し分無い。すべてのものをさらに美しく見せてくれる心地よい季節だ。日差しは強いが木陰はさわやか。朝夕少し冷え込みヒーターのスイッチを入れることもあったけれども、フリースなどは不要だった。 日を追って選手村に各国の選手団が次々到着してきた。ダイニングテーブルがどんどん増えていく。到着直後は日本人選手で集まって一つのテーブルで食事をとっていたが、各テーブルに各国のランナーが入り乱れるのに時間はかからなかった。フランス語を話す人は多いが、英語を話す人も多い。それぞれ英語は母国語ではない人たちが英語でコミュニケーションを試みるので、ゆっくり聞き、話すことが出来たので助かった。「仕事ナニシテルノ?」「イツ、ドンナフウニ走ッテイルノ?」など、万国共通の市民ランナーの話題だ。隣国ベルギーから仲間と車3台・3時間のドライブでやってきたという若夫婦は2歳の子供を妹さんに預けてのレース参加だという。ルーマニアからの警察官ランナーたちは、40時間の長距離バスの旅だったという。コーチ付きで参加しているアルジェリアやイスラエルなどの職業ランナーもいて、みなレースに向けてわくわくしている様子。  ⇔ 盛大な開会式にて、日本選手団の紹介 ⇔ 盛大な開会式にて、日本選手団の紹介イスラエルチームのコーチは目をつけた選手たちの各自のベストタイムを聞きだし、情報収集に余念が無い。彼のチームからは男子選手2名のみの参加だったが、私も彼の閻魔帳に載せられた。「ヒロコハ女子2位ニナルノハ間違イナイヨ。」と予想までつけて。このコーチにはレース中も大変お世話になった。各レースでの周回ラップをきちんと計測してくれて、おかげで女子トップとの周回ごとのタイム差も歴然、アドバイスも事細かにいただいた。おまけにISRAELと染め抜いたチームの公式ユニフォーム(新品のトレーニングウエア)までいただき、「我チームニ来テ走リナサイ、君ハイスラエルデ人生ヲ変エルノダ。」〜イスラエルにはとても移住できないけれども、このジャージを着て日本で走っていたとして、テロの標的にならないかしら???  ⇔ 第1レースの会場にて ⇔ 第1レースの会場にてレースは19日の夕刻7時から始まった。7時といってもまったく明るい。昼下がり、くらいの明るさである。体格の良い欧州人に混ざって私も一生懸命走った。レースは4日間で6レース、すべて異なった会場を走るが、私は1本ごとのレースをいかに全力で走りきるかに集中していた。スタートしてしまえば、後のことは考えない、1本ごとを大切にした。男子選手のレベルが高いので、どのレースもハイペースではじまる。なだらかな丘陵地帯が多く、アップダウンはつき物だ。毎回同じペースくらいの選手と走るので、自然と言葉を交わすようになる。 レース会場はどこも街をあげてのお祭り騒ぎだった。楽しいバンドや横断幕がムードを盛り上げてくれるし、地元の人も応援に出てくれ、子供たちも給水係をしてくれる。ボランティアがめいめいの仮装でコース係をして沿道もにぎやかだ。走り終えてから振舞われる食前酒もランナーのオアシス。クッキーやオレンジ・ナッツなどをほおばりながら、地元特産のシードルと呼ばれるりんご酒をいただく。クールダウンをする人など皆無で、みなめいめいの方法でくつろいでいる。ボランティアによるスポーツマッサージのテントも設けられ、こちらは長蛇の列だった。 私はここで初体験をした。第1ステージと最終ステージの直後、ドーピング検査を受けることになったのだ。スポーツの公明正大さを追及するための本格的なドーピング・コントロールだった。(この検査の詳細に付いては後述) 選手村を起点にバスにて30〜40分で毎回異なったレース会場に移動する。午前のレースが終われば手早くシャワーを済ませ、会場でランチをとることもあったし、宿舎に戻ってからの食事となることもあった。夕方のレースのあとは宿舎に戻ってから夕食だったので、いつも9時をまわっていた。けれども外は明るく気候もよく、疲れは感じなかった。 いただくものはみな美味しかった。レース開始日までは食堂で作っていただいた七面鳥やラム・白身魚の温かいクリーム煮など。それにフランスパンとチーズ、オリーブオイルで味付けしたサラダ。さらに必ずデザートがつく。レースがはじまれば、食堂のシェフもスタッフもみなレース会場に出向くので宅配ランチボックスだったが、温かいものはちゃんと温かくして供され申し分無かった。ビールとワインもいつも食卓に出され、「ヒロコ、飲ミ過ギナイヨウニネ。」と他国の選手から心配してもらうほど美味しかった。 朝食はパンとフルーツ、シリアル、ヨーグルト、チーズ、飲み物。普通の生活ならばこれで充分なのだが、レース当日の朝はやはり習慣的にご飯を食べたい。電子レンジでチンすれば炊き立てのご飯になるレトルトパックを日本から持っていった。毎回厨房に持っていってシェフに頼むので、ふたの隅っこを少し開封して蒸気口にすること、加熱時間は2分であること、など、シェフはすぐに覚えてくれた。 レースがはじまってしまえば、あっという間の4日間だった。選手の移動もスムーズだし、運営もタイムテーブルもきちんとしている。コースは大きな周回コースが多かったが、折り返しコースは一切無く、すべてループ状のコースだ。スタッフやエイドの配置も大変だろう。さらに第4ステージ(8.4キロ)は、それまでの持ちタイムによる総合順位の後ろのランナーからの完全時差スタート。30秒間隔で次々ランナーがスタートしていく。トップ10の男子選手は1分間隔でのスタートで、最初のランナーがスタートしたのは9時半、最後の持ちタイムトップの選手がスタートしたのは12時をはるかにまわっているのである。それでもリザルトが掲示されるのが早い。個別のレース結果に毎回のトータルタイムでの順位も張り出され、総合順位がレースごとに変化していく。会場設営も立派で、スタートとゴールにはちゃんと横断幕が張られ、ステージも設けられていた。毎回にぎやかにDJが入るが、フランス語なので私にとってはBGMだった。 レースを走り終えるにつれ、私の脚は張ってパンパンになっていったが、幸いにも走れなくなるような故障は出なかった。もちろん痛みは随所に出ているが、それで走れない、とか、走りのバランスが崩れる、ということは無かった。逆に女子トップの選手が故障悪化してきたようで、少しずつ順位差が縮まっていった。とはいえ、毎回のレースで私は彼女より後着だったので、タイム差は徐々に開いていった。走るのしんどい、と思ったことは一度もなく、第5ステージを終えていよいよあと1戦となると、「もう、明日で終わり?もっと走っていたいよ〜。」と思えるほどだった。 最終レースを前に、女子トップと2位の私の差はちょうど5分だった。しかし3位のフランス人女性との差は4分余り。走る距離は21.1キロ。女子トップのアルジェリア選手との力の差は歴然なので、たとえ彼女が脚を故障していたとしてもひっくり返すことのできる持ちタイムではない。それどころか私がレースで潰れたとすると3位のフランス人女性に逆転されることだってありうる、4分のビハインドのほうが私にとって脅威であった。とくに彼女には前日の13.8キロのレースで初めて抜かれ、その背中が遠ざかっていったのだ。あなどれない。 最終レースでは、この女子3人がけん制しあいながらのスタートとなった。お互いぴったりと脇につけ、「ドウゾ、前ニ行ッテモイイノヨ。」「イエイエ、ワタシハユックリ行クカラ。」「アナタノコトハ、気ニシテイナイカラ、先ニドウゾ。」6レース中最大の難コースといわれている21.1キロは、最初の10キロは気持ちよく下るのみ、中盤に砂利道あり、16キロを過ぎて急激なのぼりが待っているのだ。途中10キロでの私の通過順位は3位、あいだに持ちタイム3位のフランス人女性がいて、女子トップと8秒差だったという(イスラエルコーチの計測による)。十分な持ちタイムを持つ女子トップの選手はいつものレースのようにペースをあげることもしない。彼女にとって5分の差を守りさえすればいいのだから。でも、わたしは守りのレースはしたくなかった。残り10キロほどでいくら頑張っても総合順位はひっくり返らないことはわかっていたけれども、全力で走ることにした。脚は動いた。難所ののぼりも、あっという間に登ってしまったのには自分でもびっくり〜のぼりなんてどこにあったの、という感じ。そのあとの下りでも男子選手をごぼう抜きし、ゴールに駆けこんだ。「オメデトウ!」「速カッタネ!」「ヒロコガ一着ダネ!」みんなに握手をしてもらった。 ドーピング検査を受けていたので時間が切迫し、大慌てで立派なシアターに移動して表彰式・閉会式、さらに広い会場に移ってさよならパーティと、最終日はコマ送りのように過ぎていった。表彰式では、レースを完走したみんなが勝者だった。全員の名前が順次アナウンスされ、壇上にあがり完走記念品を授与された。さらに、心臓病から復帰した勇気あるランナーの表彰、最高齢者(69歳)の表彰、etc…   ↑ バンドもにぎわう閉会式 ↑ ボランティアで支えてくれたリトル・マドモワゼルたち 続くさよならパーティでは、主催者・ボランティア・各国選手団みんながそれぞれの歌や踊りを披露し、明け方まで続くダンスパーティだった。鮮やかなハッピを着てチームワーク良く日本の炭抗節を踊り、made in Japanの健康踏竹を使った青竹エクササイズを伝授。「good massage for foot!」と、健康踏竹はみんな持ち帰ってくれた。持参していた日本酒の樽酒と金杯を持って各国のテーブルを廻ると、私もいつのまにかウオッカやテキーラ、各国のビールを飲んでいた。そしてまたまた、ダンスタイム。4日間の疲れも無くずっと踊りつづけていた。踊りつづけてほてった身体をさまそうと戸外に出てみると、冷たい夜の空気の中で降るような星空。滞在中の好天にあらためて感謝した。 そして最後になりましたが、こんな私を気持ちよく送り出していただいた大阪ランニングセンターのみなさん、すべての段取りをしていただいた新日本スポーツ連盟本部と全国ランニングセンターのみなさん、そして新日本スポーツ連盟とフランスFSGTスポーツ連盟のフレンドシップに感謝し、さらに今回ご一緒させていただいた日本選手団の団長さんと選手の皆さん、そして現地でお世話になったすべてのみなさん、何物にもかえがたいすばらしい経験をさせていただき、本当にありがとうございました。 |
| <フランスでの初体験〜ドーピング検査> |
| 私がフランスの北西部で走った「ツール・ド・ペイ・ド・コー」は、参加選手300名ほどの市民ランナー中心の大会。各国招待選手が13カ国から約50名。FSGTスポーツ連盟に所属する地元の1ランニングクラブの主催である。招待選手のなかには職業ランナーもいるが、決してオリンピックレベルなどではなく一般市民レベルの大会である。が、スポーツの純粋さを追及し、公明正大のために本格的なドーピング検査が実施されていた。私が日本で参加する大阪国際女子マラソンなどではもちろん抜き打ちで実施されているのを知っているが、私などは完全に無縁のことである。一生涯でドーピング検査なんて受けることなどないだろう、と思っていたら、なんとフランスで初体験してしまった。 それは第1ステージのレース直後だった。女子2位でゴールするやいなやA4サイズの書類を持った係の女性が近づいてきて、「ココニサインヲシナサイ。」と言う。検査を受けることを受諾し、検査が終了するまで係の人の指示に従うことを約束するサインであるらしい。サインをしてすぐにドクターのいる医務室に案内された。私のほかに女子トップの選手、そして男子選手も2名ドーピング検査対象になっていた。ビニール袋に封印された採尿コップを2つ、目の前に置かれ、「ドチラカ、任意ノホウヲ、選ビナサイ。」何かの細工がしてあることなどを排除するための公平な方法であるらしい。自分の手で開封して、採尿コップを手にするが、汗だくになって走り終えた直後で尿意など催さない。他の被験者も同様で、2リットル入りの水のボトルを手渡され、もうこうなったら飲むしかない。ほかにビールの小ビンも用意されていたがキリッと冷えているものではなく、余り飲む気はしなかった。 ここまで競技服装のままだったので、汗が乾いて寒くなってきた。許可を得て、着がえる。リュックにアミノバイタル・ゼリーが入っていたので、これは飲んでおかなくては、と気付き、ドクターに申し出る。「Amino、コレハ身体ニ良イモノダ。」と、よく知られているアミノバイタルであるようだ。その後も水のボトルをほとんど空になるまで飲んで、トイレを試みるが出ない。うまく採尿を終え、検査室を出ていく選手もいて、いよいよあせってきた。廊下をとぼとぼ走ったり、その場をぴょんぴょん跳んでみたりして体内の水分が下にたまるのを待った。ぬるかったけれどもビールも飲んでみた。 結局2リットル以上の水分を流し込んでやっと尿意がやってきた。女性検査官に申し出て、トイレの個室まで付き合ってもらう。もちろん個室のドアを締め切ることは許されない。半分以上開いた状態で、採尿開始。さすがにフランス女性の検査官は、のぞきこむことは無く、私に背を向けて、手洗い器の前で水道の蛇口をひねってジョボジョボと水の流れる音を出してくれ、私もそれにつられて無事採尿終了。「トレ・ビャン(=よくできました)」。 つぎにドクターの前で、採尿コップから検査用の容器に移し替える作業があった。検査用の容器は、緑のふたと黄色のふたの2種類。これもそれぞれビニール袋に封印されたものを2つずつ、目の前に置かれ、「ドチラカ、任意ノホウヲ、エラビナサイ。」やはり事前に何かの細工がしてあることなどを排除するための方法だ。自分で選び、自分の手で開封して、容器に移し替える。ふたはとても頑丈で、手で押さえただけではきちんと封印が出来ず、かかとで押さえ込んでいた男子選手に習ってわたしも脚で踏みつけてふたをした。あとは問診。「薬ヲ飲ンデイマセンカ。」など簡単な項目。女性検査官とドクターのサイン、そして私のサインで無事ドーピング検査終了。走り終えてから実に1時間半以上たっていた。サイン入りの本人控えの書類とともに、「ドーピング・コントロール・キット」の入っていたビニール袋を「オ土産ニイタダイテモイイデスカ?」と頂戴してくるのは、さすがに抜かりの無い私らしい。 2度目に検査対象になったのは女子トップでゴールした最終レースのあとだった。実はこのとき、前日から胃痛がひどくほとんど食欲も湧かずどうしようもなかったので、レース会場についてから漢方薬系の胃薬を飲んでいた。さすがに6レースを闘う中で中盤から疲れが内臓に来たらしい。普段は胃腸丈夫な私は胃薬など持ち歩かない、が、胃痛を訴える私に日本選手団の団長さんがこの粉薬を出してくれた。団長さんは医学博士の肩書きを持つ方なので、私はドーピングのことなど気にもとめず安心してこの薬を飲んだ。 2度目の検査のときには、私は落ち着いていた。はじめは水を飲んでいたが、じきにビールに切り替え、小びんを2本飲み干し、ほろ酔い加減で検査開始。手順もわかっているのでスムーズだった。「僕ハ初メテデ緊張シテルヨ〜。」というルーマニア男子選手に「ダイジョウブヨ〜、難シイコトハナニモ無イカラ。」とアドバイスし、さらに冗談話をする余裕も。彼も私に習ってビールを飲み始めた。それにしてもレース直後にこんなにグビグビ、ビール(=フランス語ではビエール、という)を飲んでもいいのかしら? 無事に検査室を退出しても、そのあとが大変だった。何せ2リットル以上水分を飲んでいるのだから、胃袋はポチャポチャ、いったん尿意を催すと、後からあとからトイレに行きたくなる。落ち着くまで何度もトイレ通いが続いた。 私はきょうまでのところ、ドーピング違反だったという知らせがフランスからきていないので、「シロ」だったようだ。市販の風邪薬や便秘薬ですらドーピングに引っかかる成分が入っていることもあるので、競技者である限り薬は極力避けたほうが無難である。ドーピングに引っかかる成分というのは、身体に決して良いものではないから排除すべきであるからだ。「ツール・ド・ペイ・ド・コー」では、残念ながら過去にとある国の女子選手に「クロ」が出て、彼女の入賞の成績は剥奪、そして「ペイ・ド・コー」のレースから永久追放になったそうだ。自分の身体は自分で守る、これが今回のドーピング・コントロールから学んだことだった。 |
(ドーピングに引っかかる成分のリストは(財)日本陸上競技連盟発行の「陸上競技者のためのアンチドーピング・ハンドブック」を参考にしてください。)
タイムテーブル
| 日時 | 距離 | 単独レース の結果 |
合計タイム による順位 |
||||||
| Hiroko | 女子トップ | 男子トップ | Hiroko | 女子トップ | 男子トップ | ||||
| 第1ステージ | 5月19日 | 15.8km | 1:02:51 | 1:00:54 | 0:49:57 | 1:02:51 | 1:00:54 | 0:49:57 | |
| ドードビル | 19時 | place | place29 | Hassan | place52 | place29 | Hassan | ||
| Ouassiila | Ouassiila | ||||||||
| 第2ステージ | 5月20日 | 21.1km | 1:29:49 | 1:28:54 | 1:13:27 | 2:32:40 | 2:29:48 | 2:03:24 | |
| サン・バレリー | 10時 | place | place | Hassan | place41 | place35 | Hassan | ||
| Ouassiila | Ouassiila | ||||||||
| 第3ステージ | 5月20日 | 10.0km | 0:38:56 | 0:37:56 | 0:31:15 | 3:11:36 | 3:07:44 | 2:34:39 | |
| ル・トレ | 18時 | place | place | Hassan | place41 | place34 | Hassan | ||
| Ouassiila | Ouassiila | ||||||||
| 第4ステージ | 5月21日 | 8.4km | 0:32:53 | 0:32:43 | 0:26:59 | 3:44:29 | 3:40:26 | 3:01:38 | |
| オズボスク | 11時41分30秒 | place | place | Hassan | place41 | place34 | Hassan | ||
| Ouassiila | Ouassiila | ||||||||
| 第5ステージ | 5月21日 | 13.8km | 0:52:47 | 0:51:43 | 0:43:48 | 4:37:16 | 4:32:09 | 3:45:26 | |
| コート・ベック | 19時15分 | place | place | Pascal | place40 | place33 | Hassan | ||
| Ouassiila | Ouassiila | ||||||||
| 第6ステージ | 5月22日 | 21.1km | 1:29:44 | 1:29:44 | 1:16:09 | 6:07:00 | 6:05:06 | 5:01:54 | |
| イブト | 15時 | place | place | Pascal | place40 | place37 | Hassan | ||
| Hiroko | Ouassiila |
 |